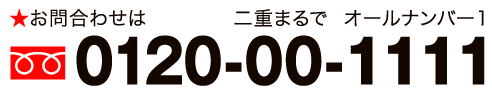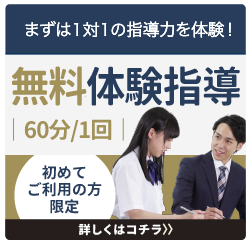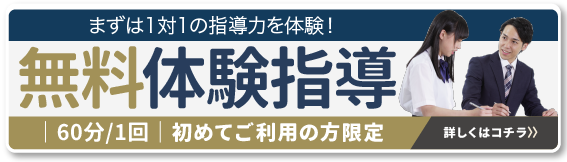【センター試験】数学 傾向分析

2018年度の問題では特にⅠAでは内容の深い理解を問う問題が出ていて
出題傾向が変わりました。
回答が以前なら素通りしてきたような内容も問題形式にされて、必ずしも明白でないことを、問われるような、深い理解が必要になっていました。
2020年度大学入学希望者共通テストの記述式を意識したような、多様な内容になっていました。
大問5問あります
第一問 必答問題で小問集合です
論理と集合が今年はありましたが、ない年もあります。
第二問は
1⃣図形
2⃣データと分析
でした。
図形は、論証を求めるような新しい形でした。難問に当たります。
データと分析は用語がしっかりと覚えているか、表を読み取れるかが
とわれていました。
データと分析は、難問が少ないので用語に慣れてしまうのが先決です。
第三問4問5問は選択問題です。
第三問は確率です。
条件付き確率が新課程になって入って、それの扱いができるかどうか、が重要でした。
第4問が新課程の整数です
センター試験の場合、ある程度形式が決まっていて、それほど難しくはありません。
第5問が図形です
知識を問われるかたちで主に数Aの範囲が出ました。難問でした
数ⅡBについて
大問5個で構成されていて、第5問は選択であまり普通高校の授業ではやらないところです。第3問「数列」、第4問「ベクトル」、第5問「確率分布と統計的な推測」は2問選択です。
問1ではラジアンの定義という基礎知識が出されました。
1⃣三角関数
2⃣指数対数関数
で出ました。難易度は平均です
第二問は微分積分です。難易度は平均です
第3問は数列で
「群数列」というものが出ました。
やや難問でした。
問4問はベクトルで基礎的な知識を問うものが出ました。
第5問は2項分布分散、確率変数の変換、母比率の推定などの公式を扱えるかがとわれました。
数ⅠAの平均点61.21前年比+0.79
数ⅡBの平均点51.07前年比―1.00
でした